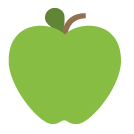県内の森林面積率が80%以上と全国的にも高く、日本一の森林県といわれる高知県は、林業や農業、漁業といった第一次産業に従事する人の割合が高いことでも知られている。第一次産業は、全国的に生産量が低下、または横ばいの状況で、森林地帯の多くは、過疎・高齢化に苦しむ中山間地域であり、担い手や後継者不足という問題も抱えているのが現状だ。
農学と海洋科学が融合する高知大学の農林海洋科学部では、山から農地、海までを含む多様性ある高知の特性を活かし、サスティナブルな地球社会の実現に挑んでいる。松本美香先生の研究室では、森林と人とのより良い関係を求めて高知県の多様で広範な森林地域をフィールドに学生の主体的な学びを重視。学生は各々の想いを具現化するべく日々の活動や研究に没頭している。
異種産業同士が手を取り合い、互いの足らずを補い、相乗効果を生み出す。そんな事象がこれからの一次産業発展の一助となるという未来を描き〈つなぐ媒介〉になるべく活動する3回生の谷風凜さん。“森里海つなぎ隊”を通して一次産業の従事者に真摯に向き合い、その内容や想いをWEBサイトで発信することで、新たな芽吹を生み出そうと活動に励んでいる。
谷 風凜
たに ふうりん○ 2003年生まれ。京都府京都市出身。
京都府内の林業系高校を卒業。入学後に農業や漁業とのつながりについて学びを深め、
一次産業に従事する人、活躍する人にフォーカスしたWEBサイト
「森里海つなぎ隊」を立ち上げ活動している。
第一次産業という仕事、携わる人の想いを発信
産業の現状や課題を伝え、森里海をつなぐ「媒介」目指す
森と里と海をつなぐ 。その純粋な想いが原点であり、モチベーションとなって彼女を突き動かす。林業や漁業、農業や畜産業といった第一次産業に従事する人たちに加え、森と里と海というフィールドで活躍している人たちにスポットをあて、その仕事や産業間の関わりについて発信する活動に取り組む高知大学 農林海洋科学部 農林資源環境学科 森林科学領域の3回生、谷風凜さん。
林業を学んでいた高校生のとき、現在の林業の課題を痛感。古くから続いてきた産業であるにも関わらず、担い手不足や輸入材の台頭といった理由から衰退している現状を知り、高校生ながらにその課題を何とか解決する道筋はないかと模索。高校の学びの中で林業が漁業や農業といった他の産業と繋がり、互いに補い合っている事例を知った。
「こんなふうに林業と他の産業が繋がっていく社会になったら、今よりもっと発展していけるかもしれない」という想いが芽生えたのは、高知大学農林海洋科学部に入学して間もなくのことだったと言う。入学当初からずっと心の中にあった想いを具現化し、実際の活動としてスタートさせたのは2回生の夏。大学の仲間と一緒に、森・里・海のつながりを発信するメディア“森里海つなぎ隊”を立ち上げた。サイトでは、一次産業に携わる人や産業同士の連携の事例などを紹介。出演者の選定や調査、リサーチからアポイント、取材に撮影まで、すべて谷さんたち学生が担うという独自のWEBサイトだ。
《森と里と海は単体ではなく自然環境の中で繋がっている》。森を林業、里を農業、海を漁業と置き換えて考えてみる。大方それぞれの産業は個々で成り立っているが、中には互いに協力し合っているという事例があるという点に着目し、森・里・海をテーマに活動に着手した。その動機は、「林業に限らず、漁業や農業など、他の一次産業と連携して発展していくために、自分たちが何か役に立てないか」と考えたことから。その思いに賛同してくれるメンバーとともに、取材対象者への出演交渉や企画の趣旨説明なども、手探りの状態からのスタート。自分たちでマイクやカメラなど機材のセッティングも勉強した。
当初は、林業や他の一次産業の現状を知り、課題を見つけて解決することができればと考えていた。しかし、現状のヒアリングを進めるうちに、「農業や漁業(他の第一次産業)は、川上から川下まで複雑に連結している。多くの人にこの“つながり”を知ってほしい」という思いへと変化していく。現在は、「自らが産業同士を繋げて課題解決まで導くということよりも、まずは一次産業で頑張っている人を広く知ってもらうこと」に焦点を当て、真摯に取材対象者と向き合い、その仕事の内容や携わる人たちの想いを発信している。
スタート当初は、谷さんの周りにあった取り組みからピックアップし、海洋系や林業系の高校教員を人選。間伐材を使った人工魚礁作りや、廃棄される運命にあるヒトデやウニの堆肥化、ウニの養殖など「海のごみ」を活用する取り組みを続ける人たちにアポイントを取り、取材・撮影を行った。「専門的な分野で活躍する人たちがいること、そして、専門分野で活躍する人同士でのつながりや新たな取り組みの展開がそこにあることを知ってほしい。自分たちが発信することが、誰かにとって何かを知るきっかけや、何かやってみようという芽吹きになり、それらがつながっていけば嬉しいです。」と谷さんは語る。一次産業に携わる人を応援し、さらに発信することで、個々に産業に従事する人たちや、情報を受け取る人たちがつながり、産業自体の発展にも結び付けられればとの展望を胸に、活動に取り組んでいる。


この日、谷さんが取材に伺ったのは、畜産農家として「あかうし」を育てる伊藤さんの牛舎。以前取材した製材業「窪内製材所」との関わりにスポットを当てる。牛舎では、製材過程で出た「おがくず(おが粉)」を牛の敷料(牛の寝床に敷くもののこと)として活用。おがくずは、他の敷料に比べても抜群の性能を持つという。ふわふわで牛の体を傷つけず、牛の糞尿をよく吸い、衛生的でもある。さらに、糞尿を吸収したおがくずは、稲の肥料として活用している。(伊藤さんは米農家でもある)
製材で使わなかったものが畜産で活用され、そこで出た廃棄物(糞尿を吸収したおがくず)も農業で活用。まさに、複数の一次産業がつながり、ある産業では不要物だったものが他の産業では価値のあるものとして使われる好事例である。
林業・農業・漁業を通して
人と人とがつながりゆく未来を創り出す
「アグロフォレストリー」や「アクアポニックス」という概念がある。アグロフォレストリーとは、 ひとつの土地に樹木と農作物を一緒に植え、農業と林業・畜産業を同時に行うことを指す。アクアポニックスとは、魚と植物を同じシステムで育てることで農薬と化学肥料も必要としない新しい農業のこと。こういった異種産業との掛け合わせで相乗効果を生み出す分野があることを知った谷さんは、身近にある事例に興味を持つようになった。
以前取材対象とした事例では、海洋の専門コースのある高校と林業の高校が協同し、間伐材で魚礁を作ることで、使い道に困った間伐材を魚の住みかに活用しようと挑戦していた。また同時に、漁で大量に混獲されるが、食用にも出来ず廃棄にも困るヒトデを肥料化するという取り組みも。ヒトデには植物の成長に必要な成分が多く含まれていることに加え、作物の大敵であるモグラなどが嫌う成分がある。すでに堆肥化に成功しており、知事の許可を得て販売している。
このように、農業と漁業、林業を掛け合わせ、お互いの特徴を活用して課題の解決に挑む人たちがいる。まさに、森が里から海へとつながっているという“つながり” を体現する取り組みにも背中を押された。
一つの産業だけで頑張るのではなく、他の産業と力を合わせることで、新たな視点で考えることができ、視野が広がる。そして新しいアイデアが生まれ、それぞれが持つ課題に対する解決方法を見つけることも可能になると言えるのではないだろうか。一次産業同士が協力し合いお互いの課題を解決していく、すなわち、林業・農業・漁業を通して人と人とがつながっていく未来を創ることができる。谷さんが立ち上げた「森里海つなぎ隊」の活動の醍醐味は、ここにあると言えよう。
アグロフォレストリー(Agroforestry)
森林農法のことで、Agriculture(農業)とForestory(森林)を掛け合わせた言葉。ひとつの土地で樹木と農作物を栽培したり、家畜を飼ったりすることで、植物同士や生態系の相互作用によって、農業と林業・畜産業を同時に行うことを指す。森の中で生態系を形成した動植物の相互作用によって、農業ができる環境の持続性を高めるという効果も期待できるシステムのこと。





問題解決のみが結果ではなく、問題を知らしめることも大切
谷さんが高知大学の農林海洋科学部を選んだ理由は?
谷 風凜(以下 谷) 山から里、海にかけての距離が近いという高知のフィールドの魅力、そして人の温かさに高校時代から惹かれていました。林業や森林環境について学んでいた高校時代に「森と里と海ってつながっているんだ!」と気付いて、林業や漁業、農業を包括的に学べる学校を探してたんです。そんなとき、高知大学の農林海洋科学部を知り、「うわ、すごい!全部揃ってる!ここしかない!」と思って進学を決めました。
大学の入学当初から、“森里海つなぎ隊”のような活動をしていこうと思っていたのですか?
谷 いえ、最初は全然具体的ではなかったんです。ただ、自分の林業の知識だけじゃなく、農業や海洋の知識を持っている人たちと一緒に面白いことができたらいいな、みたいな想いはありましたね。「林業が他の産業と繋がったり、こんなふうになったらいいなぁ」という考えだけは漠然とあって、それを友達とか先生に話していました。
取り組みを始めたきっかけは?時期はいつごろですか?
谷 あるとき先生から「学生の頃はいろんなことを見ていろんなことを学んできたらいいよ。やりたいっていう気持ちを持ってる学生はいるけど、次の段階に行けない子が多いからもったいないよね。」と言われて、「あ、自分のことだ!」って。これだけ想いがあるのに、何もやらないのは違うなって思って。何から手をつければいいのか、どうやって進めればいいのか全然分からなかったけど、「とりあえずやってみよう!」と思って動き始めたのが2回生の7月です。
実際やってみて、どう感じましたか?当初のイメージとのギャップなどはありましたか?
谷 最初は、一次産業でそれぞれの産業が抱えている課題を、別の産業で補って課題解決につなげられればと考えていました。それで課題を解決するためには一度始めた取り組みを長く継続しなければならないと思い込んだりして、一度は行き詰まったことも。思い悩んだ末、問題解決を急いだり第一義にするのではなく、一次産業で頑張っている人にフォーカスして「現状や産業の内容、問題解決の実例を広く知ってもらう」ことに重点を置く方向へと転換しました。私たちが意図的に誰かと誰かを繋ぐのではなく、“森里海つなぎ隊”のWEBサイトで発信することで、「つながるきっかけ」が生み出せたらいいな、と考えるようになったんです。それからは、「産業自体にスポットを当てる」こと、そしてそれに従事する《人》のキャラクターを掘り下げて伝えていきたいという気持ちが強くなっています。
これからどんな活動をしたいと思っていますか?第一次産業の課題感に対しての思いは?
谷 “森里海つなぎ隊”のサイトは、そこに従事している方たちだけじゃなくて、農林漁業に興味がない人、全然知らない人たちに見てもらいたいと思っています。第一次産業の課題を解決したいとか、そんな大きなことを目指しているわけじゃなくて、まずは知ってもらうこと。「なんか面白そう」とか「この方法を参考に私たちもやってみようかな」みたいな思いや新しい視点を持ってもらうきっかけを作れたらいいなと思っています。これまでは少人数で活動してきましたが、基礎ができた今は、賛同してくれる人や興味のある人を増やしていきたいな、と。私たちより下の学年の学生に繋ぎ、残していきたいと思っています。

主体的な学びをサポートし、深め活かす環境がある
谷さんが所属する森林経営研究室の松本美香先生は、森林に関わる課題に社会・人文学的手法で迫る「林業政策学」(森林政策学)が専門。「森林と人とがより良く付き合っていく」ことをテーマに、研究対象は、森林や林業の政策やその実施結果に対する評価、林業関係者の現状、そして木材をはじめとする森林からの多様な恵みの生産の質的量的変化、森林生産物を活用する林産業や加工業の動向についてなど、多岐にわたる。また学部には、先生らが運営する「農山漁村地域連携プログラム」があり、受講生はフィールド調査の手法や地域の多様な世代の人々との付き合い方などを学べるほか、卒業研究を待たず2年生からでも教員の指導を受けつつ、自分の問いを持って産業や生活の現場に飛び込み、多様な人々と関わることで、学部の学びをより深め将来に活かすことができる。
大学HPの松本先生のページには「学生は、広範な研究対象の中から自分が最も強く惹かれるテーマを決めて、調査フィールドに飛び込んでいく」とある。その言葉を体現するように、自分の信念と理想に向かって突き進む谷さん。
高知という恵まれたフィールドで、多様な産業、そしてその従事者と出会い、学びを深めていく。その先に見据えるのは、森と里と海をつなぎ、そこで生活する人と人がつながり発展する未来像だ。