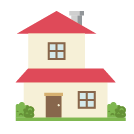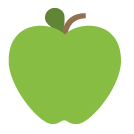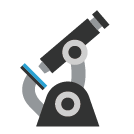日本国内の農山漁村地域では、過疎や高齢化が進み、産業のみならず地域で暮らす人々の生活基盤にも様々な課題が生じている。この要因には、多くの領域や事柄が絡みあっていることが多く、解決策を一つに絞るというのは難しい。
高知大学では、学部内の学科やコース単位で区切られた専門分野のみの視点では、問題を十分に把握できないと考え、地域の課題解決に取り組んだり、関係している様々な立場や考えを持つ人々との関わりを推進。農林海洋科学部では、中山間地域に寄り添いつつ、専門分野の垣根を越えた幅広い視野から地域の課題を把握し、解決への方策を考えることのできる力を育成することを目指している。
農林資源環境学科 森林科学領域に在籍する小川さんは、「人と自然環境との持続的な関わり方を見据え、農地や森林、海洋など“集落”での暮らしや生業」を主体的に学びたいと、休学して活動をスタートした。農林産業に従事する人々の暮らしや課題を調査するだけでなく、実際に現地に赴き、仕事や生活を共にすることで、そこでの暮らしを体験。独自の視点である「映像」という切り口でとらえることで、新しい価値を見出そうとしている。
小川 祐平
おがわ ゆうへい○ 2001年生まれ。高知県南国市出身。
生まれも育ちも高知県。小さな頃から自然豊かな環境が身近にあり、やがて林業を仕事にしたいと思うように。
高校生の時に出会ったYouTubeの映像がきっかけで映像制作にも興味を抱き、様々な体験を通して得た視点を
もとに、どんな作品を作るのか模索中でもある。興味がある場所には積極的に出向いていく行動派。
林業を生業とし、映像制作をライフワークに
自分が納得できる生き方を追求し新たな価値をつくる
「林業を生業としながら、集落の営みや魅力を凝縮した映像制作をライフワークとする生き方」。高知大学の農林海洋科学部 農林資源環境学科 森林科学領域で学ぶ小川さんが選択したキャリアはかなりユニークだ。
コロナ禍が落ち着いた2023年の春、休学を決意。前々から興味のあった大学の休学制度を利用し、県内外の様々な場所で多様な経験を積み、そこで自分が何を感じるのか再確認していくという、一風変わった活動をスタートした。期間はおよそ1年。高知県佐川町での自伐型林業の就業体験、岡山県西粟倉村のゲストハウスでの住み込みバイト、長野県伊那市では林業を体験する「働くコース」や、講演やトークセッションを通じて森の活用を考える「企てるコース」を行う〈フォレストカレッジ〉に参加。山梨県小菅村では、街や集落全体を客室に見立て、一帯で宿泊経営を行う「アルベルゴ・ディフーゾ」の概念に近しい考え方をもって、点在する古民家や施設を活用し、それによる地域振興を目指す「NIPPONIA」の試みを体感するために現地に滞在した。
「林業」「仕事」「宿」などと、分野を限定しない。《集落》と《生業》の関係性において興味のある取り組みや地域をリストアップして、自ら飛び込み、体験し、そこでの暮らしをつぶさに見つめてきたのだ。
その原動力となったのが、高校生の時に観たYouTubeの映像。四川省の農村部から中国の伝統的な文化・生活を発信する中国のYouTuber「李子柒(リー・ズーチー)」の作品だった。その美しい映像に衝撃を受け、「いつか自分もこんな映像を作りたい」との夢を抱いたが、あくまでも映像作品を作るのは趣味に留めたいと考えた。そのとき題材として影響を受けたのが、李子柒が映し出したような農村の原風景。そこで日本の集落や宿などを被写体にしたいと考えたときに、森や里に関わる生業を持つことで、両立が叶わないかと考え、林業に携わっていきたいという思いが同時に芽生えたそうだ。
まずは林業の知識や技術を習得したいという思いから、林業に接する機会が多い高知大学に進学。コロナ禍で外の世界と隔絶された期間を経て、実地研修やフィールドワークなど学びを深めるうち、「もっと多くの体験を積みたい」という思いが強くなり、ユニークなキャリアを選択した小川さん。彼の行動力には目を見張るものがあるが、高知大学 農林海洋科学部ならではの自由で闊達とした風土も背中を押したと言えるだろう。


大学という枠を超え、広い視野から地域課題と解決への方策を模索
学部独自のプログラムを活用し、主体的な学びを深める
小川さんが在籍する高知大学の農林海洋科学部 農林資源環境学科、松本美香先生の研究室では、各学生がオリジナリティあふれるテーマのもと、学びを深めている。
そもそも農林海洋科学部は、高知県の恵まれた立地条件である豊かな自然との距離の近さを活かして、座学だけではなくフィールドでの学びも充実した環境で「人と自然環境との持続的な関わり方としての農地や森林、海洋のマネジメントの知識と技術」を主体的に学んでもらうことを目指してる。
高知県という場所は、太陽の恵み豊かな土地での施設園芸や果樹栽培も盛んであり、一つの県の中に亜熱帯から亜寒帯の特徴を持つ樹木が育つ。さらに太平洋に面しており、黒潮の恵みがあり、沖合近くには深海も。山から農村、海までの広範なフィールドが常に身近にあるという環境だ。そして、人口減少・少子化・高齢化の先進地だからこそ、地域の取り組みや施策にも特徴がある。
松本先生の専門は、林政(林業政策学)と呼ばれる森林科学の分野における社会・人文科学的なアプローチ全般(政策学、経済学、社会学、民俗学、文学など)を指す分野で、その領域は多岐にわたる。具体的には、森林・林業に関する政策や課題を取り上げ、物流や商流、関係者、情報などに焦点を当てて調査し、問題点を明らかにして解決策を提案する。わかりやすくいえば「森林と人とがより良く付き合っていくための研究」。学生は皆、その想いを胸に地域に飛び込んでいく。
高知大学 農林海洋科学部には「農山漁村地域連携プログラム」という履修科目が存在する。これは、地域に寄り添いつつ、専門分野の垣根を越えた幅広い視野から地域課題を把握し、解決への方策を考える力を育成することを目指すもの。以前から学生の中には、大学という枠を飛び越えてもっと広い領域で学びを深めたいと考え、学外に活動や研究の機会を求める学生がいた。そういった活動や研究を松本先生ら人文社会系の学部教員と大学がサポートし、手法や知識のバックアップをするとともに、その学びに対し単位認定までする仕組みである。所定の単位を修得した学生には、プログラム修了認定証が授与される。
小川さんは、休学期間に実際の現場で自ら問題意識を持って調査を行い、学びを深めてきた。そして今、「農山漁村地域連携プログラム」に関わる教員らに合同ゼミで様々な角度から助言を得て卒論を進める。休学制度と学部独自のプログラム、双方のメリットを活用し、自身の“主体的な学び”を深化させているのだ。

このような学修環境の中で、小川さんは自らの心の赴くままに、興味のある仕事に就業し、間近に見たい風景を肌で感じ、暮らしてみたい場所を訪れ、出来る限りの体験を積んできた。
その活動は、「自分の気持ちの再確認と、新たな興味の発見」だったと言う。まず、林業という仕事に対して「拒絶反応がなかった」という再確認だ。これは、高校の頃から「林業を仕事にしていきたい」という思いがあったものの、本当に自分はそれを仕事にしていけるのかという懸念を払拭する機会となった。
自身の行動を「究極の自己満足」と表現する小川さん。しかしその自己満足の先に、集落の課題解決や地域の持続可能性の追求、日本の原風景や伝統文化を守り、未来へとつないでいく、といった“他者貢献”があるのではないだろうか。


農林地域での体験を通じて観光や暮らしの視点からとらえ
フォーカスし直す
「映像制作」と「林業」って、なかなかギャップがあるように思いますが、その真意は?
小川 祐平(以下 小川) 李子柒さんの映像は農村や地域の原風景というものに興味を持つ大きなきっかけにはなりましたが、映像制作はあくまでも趣味、ライフワークとしてやっていきたいこと。お金を稼ぐための仕事、いわば生業としては、林業がいいと思ったんです。映像制作がメインなら、映像系の学校に行って専門的な技術や知識を習得するという道もあったかもしれませんが、映像制作を「お金を稼ぐ手段=仕事」にしたくないな、という思いが漠然とあって。自然と共に生きながら集落で生活する「林業」を仕事にすることで、映像制作の題材となるものが身近にある環境に身を置けると思い、選択しました。
高知大学の農林海洋科学部に進んだ理由は?
小川 もともと林業の現場、たとえば伐採職などに将来就きたいという気持ちから、知識も実務的な技能も身につけたいと思っていました。高知県佐川町で、地域おこし協力隊制度を使った自伐型林業を盛んにやっていて、いつか参加したいという思いもあり、技能を身に付ける前に林業を学ぶなら高知大学が最適ではないかと考えて志望しました。
3回生の終わり頃、休学制度を活用していろんな体験をされたということですが、何かきっかけがあったんですか?
小川 きっかけがあって始めたことではなく、ずっと自分の中ではやりたいと思っていたことなんです。でも、2020 年4月に入学してすぐに新型コロナ感染症が広がり、1回生はほとんどリモート授業。自宅にこもる生活が続き、外の世界への思いが余計に強くなったという部分もあり、コロナ禍が落ち着いてから、行きたい場所や興味のある体験をリストアップして、休学に向け着々と準備を進めました。休学制度を利用したのは23年4月〜翌3月まで。県内外に赴き、林業に関連する会社で働いたり、興味のある地域で過ごしてみるという体験をして、今に至るという感じです。
自分が目指す映像作品について、将来的な展望は?
小川 正直自分の中で、どんな映像作品をつくっていくのかという具体的なビジョンはまだありません。ただ、自分がいつか作る映像作品の舞台は、日本の原風景とされるような地域や集落だと思っています。そこでの暮らし、自然、住民同士の関わりといった要素を盛り込み、映像作品として完成させたい。見ていただきたい対象は、ある程度社会経験を積んだ人たちです。作品を見てもらうことで、新しい生き方や暮らし方を発見するきっかけとなったり、集落や森林というものに想いを馳せてもらえたら、と思っています。

失われゆく日本の原風景と農村暮らしにスポットを当て
資源としての価値を高めたい
農村地域での作業や暮らしを疑似体験したなかで、注目されがちな観光名所だけに必ずしも価値があるわけではなく、訪問者が「良いな」と思う体験や思い出、それこそが価値のあるもの(=資源)だという思いに至った小川さん。集落やそのエリアの自然まるごとが「スタジオ」で、地域住民や訪問者は「演者」、宿泊施設も舞台装置(被写体)として重要だと考えている。
いろんな場所や環境に身を置き、そこで自分が感じたことや体験をいつか映像という世界で表現したい。それが、森や農村に暮らす人々の変化を記録するものにもなり、観る人に農村地域の課題を考えてもらうきっかけになればという思いもある。
日本の社会課題として横たわる、限界集落の問題。その解決策の一つとして、いつか小川さんの手掛ける映像作品が、社会や人々にとって新しい価値観を見出すきっかけとなる日がくるのかもしれない。
森林で過ごす時間と生活Styleを模索する小川さんのYouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@asuta.pla-no