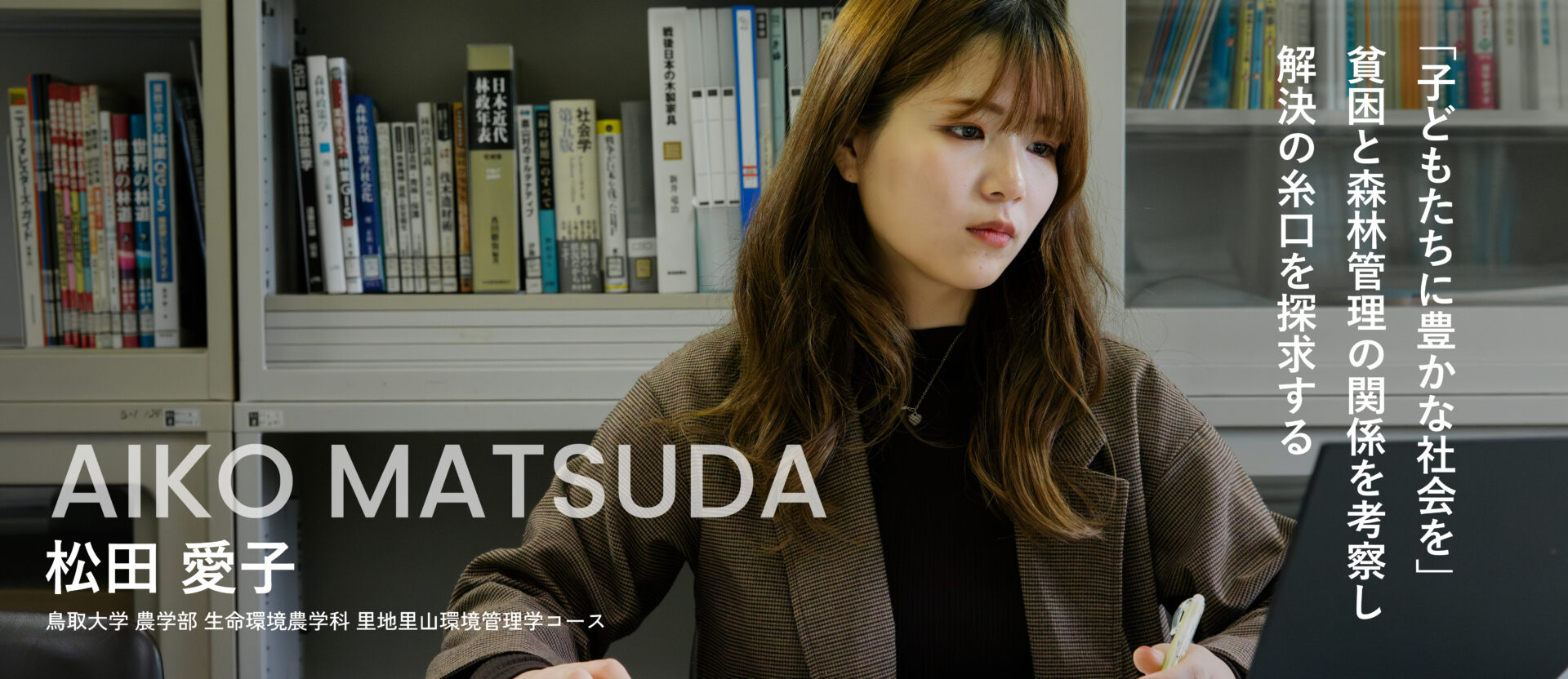

海外、特に東南アジアでは、古くから住民が森林を切り開いて農地を作り、収穫した農作物で収入を得てきた。従来の社会構造の中、伝統的な焼き畑や林業の範囲であれば問題はなかったが、人口増や、より多い収入を得て経済的な豊かさを求めるあまり、森林が容易には回復しないほど広範囲に切り開いてしまうという荒っぽいやり方を進めているという現状がある。乱開発によって森林が減少し、持続可能ではなくなっていることが世界的に問題になっているのだ。解決するためには、森林の利用を抑制しなければならないが、一方で、古くから伝統的に森林を利用して暮らしてきた人々の人権を無視してよいものかという声も上がっている。
鳥取大学農学部生命環境農学科の松田愛子さんは、こういった問題の解決法として東南アジアで導入されている、住民が主体となって森林の管理を行う「参加型森林管理」に着目。この管理制度が地域住民の生活に与える影響や貧困問題との因果関係を解明し、住民にとって本当は何が必要なのかを考察していくという研究を卒業論文のテーマに選び、取り組んできた。理想として描くのは、世界中の子どもたちが教育を受けられる社会の実現。貧困と森林管理という視点から考察し導く結論が、その解決の一助となる未来を夢見て、研究に没頭する。
松田 愛子
まつだ あいこ○ 2002年12月1日生まれ。兵庫県宝塚市出身。
通っていた小・中学校で社会貢献の取り組みが行われており、「奉仕部」で発展途上国への支援活動に
進んで参加した。鳥取大学農学部では、森林と貧困についての関係に問題意識を持ち卒業論文の
研究テーマに。研究を続けたいという思いから、卒業後は京都大学の大学院へ進学することが決まっている。
森林×人×社会の持続可能な関係を
制度や政策から追求する
開発途上国における砂漠化などの環境問題や、食料生産に関わる農業問題の解決、環境と資源の利活用や有用生物資源による食料生産の推進などを通じて人類の生存や生活に貢献することを目標に、地域規模(ローカル)から地球規模(グローバル)までの広範な課題の解決に農林学の立場から貢献する人材を養成。専門的な知識や適正な対応技術を学ぶことができる鳥取大学農学部生命環境農学科。里地里山環境管理学コース 農林業政策学研究室の助教、芳賀大地氏の研究室では、森林と人、そして社会がどうやって良い関係を築けるかということを考える農林業政策学を中心に研究や教育を行っている。農林業政策学では、持続可能な森林利用のためにどんな障壁や問題があるのか、あるいは森林の状態をもっと良くするために経済、政策、社会、文化、歴史といった側面からアプローチするといった分析を中心に行うほか、一つの政策が施行された際に、林業従事者だけではなく、森林にあるキャンプ場を訪れる人のように地域の人たちにどのような影響があり、もし課題がある場合はどう改善していけるかということを模索。また、現状に問題が起きているとすればどこに原因があるのかといったことを調べている。
例えば、全国で問題になっている獣害被害の対策としてジビエ肉を食料として有効利用して資源化するという取り組みについて。鳥取県は他県よりかなり早い段階でこの取り組みをスタートし、安定的に運営できているのだが、単に政策という観点以外からもその要因を探るなど、実際の事業者の取り組みや連携といった視点から、社会と森林との関わりを研究している。
現在、芳賀先生の研究室に所属する4回生の松田愛子さんも、社会と森林の関係に関心を寄せている一人だ。世界の途上国で起こる貧困と森林管理の問題に向き合い、その解決策を模索するため研究に没頭している。


東南アジアなど途上国で取り組まれる参加型森林管理が
地域住民の生活に与える影響を考察
松田さんは、小・中学校時代から発展途上国の貧困、それに起因して教育を受けられない子どもたちがいることに心を痛め、この問題に関心を寄せていたと言う。「“貧困による教育問題”と“環境保全”という2つのテーマには以前から興味がありました。大学で森林管理や林業政策について学んでいくうちに、その問題を解決するには、地域住民の生活と森林の活用方法の関わりがキーポイントになること。例えば森林管理が住民の生活にこういうふうに役に立つよねとか、こういう制度によって貧困の脱却を試みようとしている、ということがあって。この“貧困”と“森林管理”というものが繋がったんです。」
そこで松田さんは、東南アジアを中心とした農村部に住む人々の貧困について問題意識を持って卒業論文の研究テーマに設定。調査方法としては、貧困層の生活環境や、参加型森林管理に関する文献調査と統計整理を主に行った。「参加型森林管理が東南アジアで行われ始めたのは1990年代後半頃からなので、1990年代、2000年代、2010年代の年代に分け、たとえばフィリピンの1990年代に行われていた参加型森林管理、2000年代、2010年代と調べていきました。さらにラオス、ミャンマー、インドネシアとそれぞれの文献を調査することで、参加型市民管理の当時に関する文献からメリットやデメリット、計画の成り行きなどについてつぶさに調べました」と、松田さんは研究の進め方について話す。
貧困のレベルについては、フィリピン、ラオス、ミャンマー、インドネシア各国の国ごとの統計調査やインフラの整備率、中学校までの就学率などをデータとして利用。世界銀行や国連開発計画が発表しているデータを用いて、各国・各年代の貧困段階を3段階に分類し、段階別に参加型森林管理の運用実態を地域住民の影響に着目して調べた。住民が貧困生活から脱却するためには、教員や公務員といった「農外収入」を得ないことには難しい。松田さんは「土地を持ってない人々であれば、教育を充実させるなど他の方法で貧困を脱出する方法があるという先行研究がありました。そこで貧困段階によって、参加型森林管理が住民の生活に与える影響も違ってくるのではないかという仮説を立て、4年次からは自分が立てた仮説を明らかにするためにさらに必要な論文を探し、考察を深めました」。このような手順で参加型森林管理の成功度合い、貧困のレベル、住民生活へ与える影響の相関性を改めて検証した。
この調査・研究から導き出されたのは〈1.森林管理としてはうまくいっているが、住民生活が犠牲になっている〉〈2.両方ともうまくいっていない〉〈3.住民生活には大きな影響がないが、森林管理としても効果を上げていない〉という様々な状況があること。つまり《対象地域の中で最も深刻な貧困状態にあり、農業・非木材生産物が主な収入源となっている地域では、地域住民は制限を大きく受けることなく慣習的な土地利用を継続しているため、参加型森林管理制度による地域住民への生活に悪影響は見られなかった。一方、貧困度が中~低程度の地域においては制度の運用はより実態をもって行われていた。しかし、こういった地域では現金収入の重要性が高まることから、収益率が低く森林利用の制限が厳しくなる参加型森林管理は住民へのインセンティブが希薄なため定着が困難。》となる。このような考察から、参加型森林管理による地域住民の生活の向上は、実施地域における貧困の程度に影響されると結論づけた。
松田さんは、この研究が「世界の貧困問題を解決し、誰もが教育を受けられる社会の実現に寄与する、それに少しでも役立てれば誇らしいなと思います。」と話してくれた。
参加型森林管理
地域住民が主体となって森林管理を行う制度のこと。これまでは国や州といった政府機関が直接管理したり企業に権利を譲渡するといった、地域住民が関わらない形での森林管理制度が主流だったが、住民の生活を無視することで反乱や乱開発が広がるなど問題が多かった。そういった背景から生まれた「参加型森林管理」は、政府や自治体による森林管理に住民が参加したり、委譲されたりして森林を管理する仕組み。

3回生の終わり頃にはこのテーマで研究を進めようと決意し、4回生の1年間はひたすら文献や論文を読み込み、統計などを調査してきた。読んだ論文は50以上。数多の文献や参考書籍など、時には挫けそうになる膨大な資料を前に、支えてくれたのは同じ研究室の仲間だった、と松田さんは話す。「芳賀先生からも、私たちの学年は元気いっぱいだね、と言われます(笑)。定期的に研究室全員で進捗共有などの発表があるのですが、それ以外の時も相談したり、時には弱音を吐いたり、みんながいてくれたからここまで頑張れたかなと思ってます。」同じ環境でそれぞれの目標に向けて頑張る仲間の存在も、松田さんの志を支えてきた。


子どもの頃から抱いた貧困地域への問題意識
森林管理の視点から研究
鳥取大学に進学し、芳賀先生の研究室を選んだ理由は?
松田 愛子(以下 松田) 自然資源の保護や海外の森林政策といったことに興味があったのと、理科の先生になりたいという夢があったので、どちらも学べる鳥取大学農学部を志望しました。林業政策を研究している研究室を探したところ、当時のチューター(学生への学習助言を行う人)から海外の事例にも通じておられる芳賀先生をご紹介いただきました。
貧困や、教育を受けられない子どもたちがいるといった社会問題に関心を持ったきっかけは?
松田 通っていた小・中学校の姉妹校がフィリピンにあって、フィリピンの人々の生活を知る機会があったんです。貧困によって教育を受けられない子どもたちがいることを知りました。その学校に「奉仕部」というボランティア活動をする部活があり、募金をフィリピンの子どもたちに送ったり、中学校でホームレスの方に帽子を編んで毎年届けたりという活動もしていました。そういう社会貢献に力を入れている学校で自然にそういう関心や意識が芽生えたのだと思います。
卒論のテーマを選んだ理由は
松田 自分の根底に、貧困を解決したい、教育を受けられない子どもたちの数を減らしたいっていうすごく大きなテーマがずっとあって。そういう問題に少しでも寄与できればという思いからです。わずかでも何かの役に立つ研究になればと思い、選びました。
研究に際しての芳賀先生からどのようなアドバイスが?
松田 貧困が森林減少の大きな要因として指摘されているということを授業で教わって。じゃあこれをどう研究していこうかと思っている時に、国や地域によっても制度や事情は違っていることもあるので、関係のある論文を調べ直して貧困と森林管理のつながりを再整理することができればいいものになるんじゃないか、とアドバイスいただきました。
研究で大変だったことはありましたか。
松田 3年の終わり頃から、森林管理や各国の貧困層の現状などの知識を蓄えるために文献をずっと読んでいましたが、卒論の研究でも文献を50本以上は読みました。現地調査に行くことは出来ないので、文献の中からいかに統計や資料を見つけ出して裏付けを行い、説得力ある論文にするかが大変でした。
鳥取大学卒業後は京都大学の院に進学するそうですね。教職を目指しているそうですが、その後の進路の予定は?
松田 最終的には教員になりたいという気持ちはあります。教職の場合は教員採用試験に受かれば何歳からでもなれると思いますが、その前に社会経験をしないまま子どもたちを指導することに不安もありまして。それに新卒じゃないとできない仕事や入れない企業もあるので、まずは社会経験を積み、それを活かして、いつか教職に就ければと思っています。
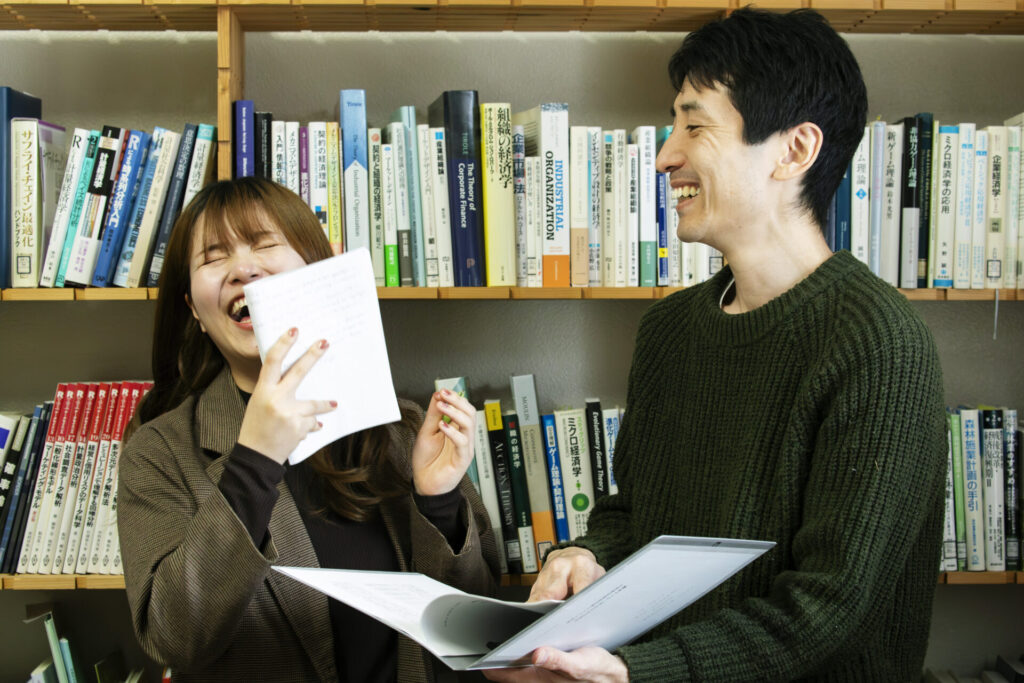
検証と研究、考察から貧困問題解決の一助となることを目指す
未来の子どもたちの豊かな世界を守りたい
貧困をなくし、教育を受けらない子どもたちの数を減らしたい。未来の社会を担っていく子どもたちの豊かさを守りたいという想いがずっと根底にある、という松田さん。卒業後は京都大学の大学院に進学し、森林人間関係学研究室に所属する予定だ。「卒業論文は文献からの検証だったので、現地に入らないと見えないこと、わからないこともいっぱいあるなと実感しました。今後は現地に入って、明らかにされていないことも調査していきたい」と話す。
貧困の解決と森林の持続的活用。豊かな森林をどのように管理し、どうすれば住民がその豊かな恩恵が受けられるかという問題を解明し、世界から貧困に陥る子どもたちがいなくなるよう、持続可能な未来に向けて、適切な森林管理の在り方を検討する。松田さんが描く理想の社会の実現に向けて、彼女の研究はこれからも続いていく。




