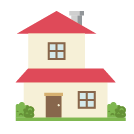シカやイノシシなどの野生鳥獣による農作物被害は年々深刻化しており、2023(令和5)年度の全国における農作物被害は164億円(前年度比8億円増)にのぼった。その影響は経済的影響のみにとどまらず、営農意識減退によって耕作地放棄や離農を招き、さらには生息環境拡大を引き起こし、人里への侵害や森林の荒廃にもつながっている。長年地方財政を悩ませてきた野生鳥獣だが、ここに来てようやく明るい兆しが見えている。2023(令和5)年度のジビエ利用量は2,729t、前年度比30%増と過去最高を記録。6割が食肉として、3割がペットフードとして利活用されており、一般にも「ジビエを美味しく食べる」意識が高まりつつあることがうかがえる。
現在のムーブメントに先駆けてコロナ禍の只中であった2021(令和3)年に取り組みを開始した「IPUジビエ」。IPU環太平洋大学(岡山市東区瀬戸町)経済経営学部 現代経営学科の扇野ゼミのプロジェクトである。地域課題解決から派生した取り組みでありながら、食肉加工のみならず現在もなお廃棄されている皮部分までもアップサイクル。《命》を余すことなく、すべて利活用する——全国でも稀有な事例として注目されている。
IPUジビエ
IPUジビエ(IPU Gibier) IPU環太平洋大学サステナブルブランドプロジェクト(扇野ゼミ)
2021年9月、経済経営学部・現代経営学科の「ブランド戦略論」授業から始動。授業修了後も自主的に継続したい学生を中心に、社会課題解決型ウェルビーイングを目的として活動。2023年から扇野ゼミが始動し、ESD(Education for Sustainable Development・持続可能な開発のための教育)としての側面、非認知能力の育成としても高く評価される。「2022年度ブランディング事例コンテスト中小企業庁長官賞」、「令和6年度岡山市学生イノベーションチャレンジ推進プロジェクトグランプリ」、「おかやまSDGsアワード2024」他、数々の受賞歴を誇る。
「サステナブルブランドプロジェクト」
地域課題解決体験型カリキュラムとしてジビエに取り組む
企業ブランディングなど中小企業が内包する課題解決の仕掛人として幅広く携わってきた扇野睦巳さん。IPU環太平洋大学からブランド戦略論の非常勤講師として招聘されたのはコロナ禍の只中である2021年のこと。大学は市街地から離れた山の中とも言える場所に位置しており、世間からも学生自身も《郊外にある大学》という認識が根強いのは否めなかった。
「裏を返せば、都会の大学にはできないことができるってこと」。そう考えた扇野氏は、長年地域を悩ませている野生鳥獣被害に着目。捕獲されたシカやイノシシのほとんどが廃棄処分されてきた過去に比較すれば、食肉素材としてのジビエは市場へ徐々に理解が浸透していたものの、学生の認知度は0に近い状況だった。さらに、皮革の利活用に至っては総捕獲量の1%にも満たないのが現状であった。かねてよりジビエレザーやエシカルレザーの普及促進を手掛けてきた「一般社団法人やさしい革(東京都墨田区/代表理事:山口明宏)」の理事として名を連ねていた関わりから、《肉も皮も》利活用できる、全国でも稀な包括的ジビエプロジェクトとしてスタート。学生からも「やってみたい」と好意的な声が上がり、順調に進んでいくかに見えた。
そもそも扇野氏の担当は「ブランド戦略」であり、当初はこの活動も、ジビエを媒介とした地域ブランド構築の一例であった。そのため授業内容も概要論の範疇を超えておらず、座学だけでは学生の心に響かないと痛感した、と扇野氏は振り返る。「これまで企業には賞賛されていた内容が、学生にはあまり響かない。これではいけない、とすぐに内容を改めることにしました」。
そこで「体験型授業」としてスイッチ。「理論だけを押し付けても、経験の少ない学生には腹落ちしない。泳ぎを教えるのに水に入らずに方法論だけを一方的に伝えるようなもの。せっかく生きた教材が身近にあるのだから、まずは水に飛び込んでみよう! と」。

扇野 睦巳
おおぎの むつみ ◯1970年生まれ。岡山県岡山市出身。
結婚・出産を経て、子育てと両立しながら法政大学に進学し、ブランディング、マーケティング、小売業に関する研究に従事。その後、中央大学大学院(MBA)に進学し、100年企業におけるビジネスモデル・イノベーションを研究する。また、野中郁次郎教授が提唱するSECIモデルを、デザインや教育の領域に応用した知識創造の実践にも取り組む。
2015年5月には東京都にて株式会社ファーストデコを設立。多岐にわたる事業領域で活動し、各種受賞歴を有する。
2021年9月より環太平洋大学経済経営学部現代経営学科の非常勤講師に着任、2023年からは特任准教授として教育・研究・実務の融合に取り組む。
デザイナー、研究者、教育者、実務家として、人と企業の理念化を推進している。
一般社団法人やさしい革(MATAGIプロジェクト)
「工場排水のクロムがゼロ」「仕事のストレスがゼロ」「動物のストレスがゼロ」「不公平・不公正な取引がゼロ」の4つのゼロを提起し、人と自然と環境にやさしい「ラセッテーなめし製法」を活用。次世代につなぐ皮革消費文化を推進している。駆除したイノシシやシカの原皮(剥いだままの毛の付いた生の状態)を預かり、革素材にして産地へ還す「MATAGIプロジェクト」では、「頂いた命の皮を最後の1枚まで大切に使い切ること」を目指し、獣革利活用の情報発信や講座、販売会支援など活動の幅を広げている。
https://russety.jp/yasashii-kawa


ゼミのメンバー全員で調理、キッチンカーの準備、提供まで実施した。
卒業生や専門家の力を借りて第一弾「ジビエラーメン」が完成
地元企業コラボで続々と商品化が実現
最初に行った体験型授業は、山でのフィールドワーク。IPU第1期卒業生で、「株式会社どんぐり(岡山市北区門前)」を経営する石原佑基氏の協力により、罠捕獲の現場に立ち会うことができた。捕獲から〈と殺〉〈解体〉〈加工〉を目の当たりにして《命》と真っ向から向き合った。初めて〈と殺〉を間近に見た学生たちから「肉も皮も、骨一本も無駄にしたくない」との声が自然に湧き上がり、第一作目となる開発商品は「ジビエラーメン」に決まった。
レシピの開発は、ジビエ料理の第一人者である中川妙子氏と麺の専門家である冨士麵ず工房の波夛悠也氏に依頼。コロナ禍真っ只中の2022年1月に岡山市内の飲食店を貸し切り、スタートから4カ月というわずかな期間でテストマーケティングを兼ねた試食会まで漕ぎ着けることができた。
2度に渡る試食会で手ごたえをつかみ、「IPUジビエ」ブランドが誕生。授業が終わった後も活動できるよう「IPU環太平洋大学サステナブルブランドプロジェクト」を立ち上げる。卒業した先輩からのバトンを受け継ぎ、毎年数名の学生がフィールドワークから商品開発、販売戦略構築と一連のブランディングに関わっている。2023年から扇野ゼミメンバーがプロジェクトを駆動。これまでに誕生した商品はカレーパンやアスリートカレー、シカ革のカップスリーブやイノシシ革のコースターなど多岐にわたる。
2022年に開催された「第4回SDGs提案(SDGsオンラインフェスタ)」グランプリ受賞をはじめ、「ブランディング事例コンテスト2022(一般財団法人ブランド・マネージャー認定協会)」中小企業庁長官賞、「おかやまSDGsアワード2024」など、今日に至るまで数々の受賞歴を誇り、多方面に影響を与えている。

きっかけは「好奇心」
自分のルーツと照らし合わせ、拡がる可能性を模索
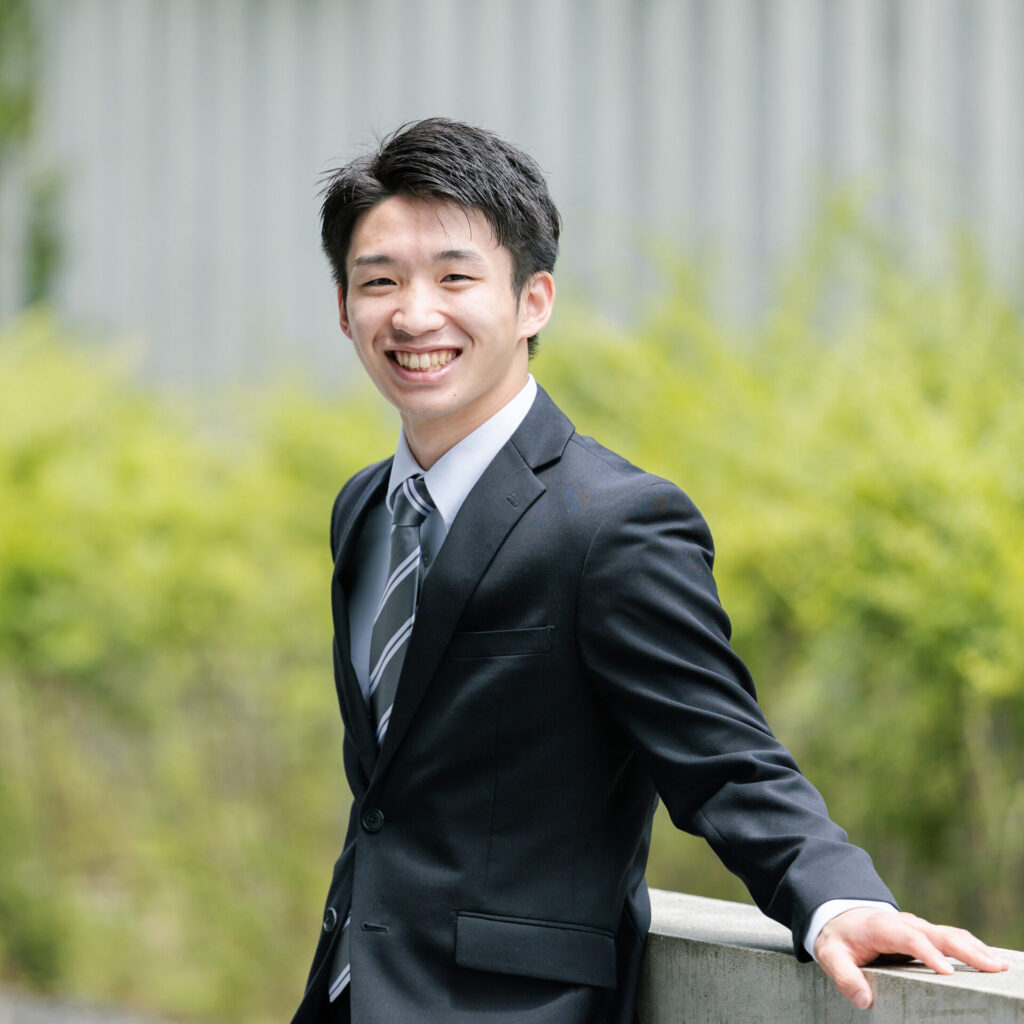
前田 一成
まえだ かずあき ◯2003年5月生まれ。福島県東白川郡鮫川村出身。
IPU環太平洋大学 経済経営学部 現代経営学科4年生。マーチングバンド部所属。高校時代にマーチングにインスピレーションを得て進学。ゆくゆくは兼業農家である父親の力になりたいと考えている。

田中 万智
たなか まち ◯2003年8月生まれ。福岡県北九州市出身。
IPU環太平洋大学 経済経営学部 現代経営学科4年生。マーチングバンド部所属。実家が自営業だったことから経営学に興味を抱く。経営コンサルタントを目指し、就職活動中。
なぜ「IPUジビエ」ゼミに参加しようと思われたのですか?
前田 一成(以下 前田) 僕は福島県の、この学校よりもさらに山間部にある村の出身です。父は兼業農家で、無農薬米を栽培しています。「鹿がトラックにぶつかってきて壊された」「イノシシに畑を荒らされた」と子どもの頃から鳥獣被害は耳にしていて、シカやイノシシは《害獣》という認識でした。
「IPUジビエ」を知ったのは授業の中で。「美味そう!食べてみたい」という食欲がきっかけでした(笑)。
田中 万智(以下 田中) 私はまったく縁がなくて「ジビエって何?」って感じでした。良いも悪いもなく、先入観がないからこそ未知の世界を知りたいっていう、好奇心が大きかったですね。実際に食べてみても違和感なく単純に「美味しいな」と感じました。
「IPUジビエ」ではどんな取り組みをされたのですか?
前田 と殺には参加していないのですが、加工されたものをどう利活用していくかということに課題を感じていました。僕は父の無農薬米と組み合わせて、これまでにないものを作りたいと思って。米に含まれる農薬はただちに影響することは少ないけれど、ずっと食べ続けることで体に蓄積されてしまう。父はいつも「子どもたちに安全な食べ物を食べてほしい」と言って、手間ひまかけて無農薬米を育てていました。手間がかかる上に儲けも少ないのが現状ですが、無農薬米とジビエはこれからの食文化において、もっと価値が認められるものになるのでは、と思っています。
田中 2024年からはキッチンカーで「IPUジビエ」のオリジナルメニューとしてカレーパンやジビエ丼を提供してきました。「IPUジビエ」以外にも先輩から受け継いだメニューが多く、「IPUカルチャー」としてベトナム留学生の先輩が開発されたフォーは特に評判が高くてファンも多い。地元企業からも興味を持っていただけました。今回のオープンキャンパスでふるまった「ジビエ丼」は、私たちが2年生の時に受講したマーケティング総論の授業で前田君と一緒に考案した商品で、思い入れのある自信作です!まだまだ知られていないので、今後はお子様にも食べていただけるような場所にも行ってみたいと思っています。
「IPUジビエ」での取り組みを今後、どう生かしていきたいですか?
前田 僕は、経営者になって儲け、両親に恩返しをしたいという想いを中学生の頃から持っています。父が一所懸命、無理を押しながら無農薬米栽培にこだわる姿や、僕のやりたいことをやらせてくれていることを考えると、多くの経験を積んで人と交わり、将来に生かすためにどんなことでも自分の糧にしていきたいと思っています。福島ではイノシシの頭数が10倍に増えたことも聞いています。福島でジビエ産業を根付かせるような取り組みができればとも考えています。
田中 私は地元の福岡に戻り、地元企業を支える経営コンサルタント会社への入社を志望しています。「IPUジビエ」の取り組みは、社会課題を解決するブランド戦略の視点としてとても有意義かつ有用だと感じています。この学びを生かして、今度は自分が主体的に、戦略やマーケティングをコンサルティングする側になれたらと思っています。


2030年までに「IPUジビエ」が目指すSDGs
教育的&社会的意義もはらんで成長
「IPUジビエ」はゼミの中で生まれ、育まれたものが次のゼミ生へ受け継がれる形で継続してきた。「IPUジビエ」の他にも「サステナブルブランドプロジェクト」には、ベトナム文化との融合やエシカルスイーツ、アスリート向け社会貢献ブランドなど、複数のファミリーブランドが同時多発的に展開しており、それらのブランドとのシナジーも形成されている。
2030年までに達成を目指す「IPUジビエ」のSDGsにおけるKPI(重要業績評価指標)として、「衣・食・住を合わせた50アイテムの商品化」に加え、各種ステークホルダーとの協働などが掲げられている。これにより、学生たちの自律的な学びと行動が促進されている。
本プロジェクトを主導する扇野氏は、学生が「IPUジビエ」に携わることで、生産性の向上や「理念と経営の両立」を実践的に学ぶことにも期待を寄せている。学内外の多様な人々とのつながりを通じて、《命》と向き合う姿勢を育み、エシカルかつエコロジカルな価値観を体験的に習得することは、AIでは代替できない人間固有の学びであり、普遍的な意義を持つと捉えている。
瀬戸内の山中で生まれたサーキュラーエコノミーを実現するプロジェクトがブラッシュアップを続け、「《命》を大切にしてくれる人の元へ届ける」という当初に自然発生した想いがパーパスとなり、大きく広くらせんを描くように、今も成長し続けている。
IPUジビエの詳細はこちらから
https://ipu.okayama.jp/ipu-gibier/