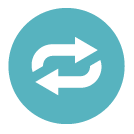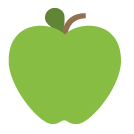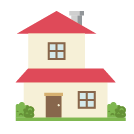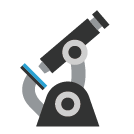「農福連携」は、農業の担い手不足と障害者の就労機会の少なさという社会課題に対し、農業と福祉が手を取り合い解決を図る取り組みとして2009年頃に始まった。農園での作業を通じて自立支援につながるなど、成功事例が各地で生まれ、さらに農林水産省と厚生労働省が連携し、全国的に推進するための体制を整備。「農山漁村振興交付金(農福連携型)」の創設、2024年には「農福連携等推進ビジョン(改訂版)」が策定されるなど、補助金制度やガイドライン整備を通じ、共生社会実現の一助となっている。
一方で、森林分野での応用「林福連携」は、近年注目され始めた新たな実践領域だ。伐木や造林といった重作業のイメージが先行する林業においても、苗木管理や木工など安全性を確保した多様な作業が存在し、福祉的就労との接点が見出されつつある。
京都大学の大学院農学研究科 森林・人間関係学研究室に在籍する保積さんは、「林福連携」を新たな価値としてセグメンテーションするべく調査・研究をスタート。現場に入り込み当事者の声に耳を傾ける保積さんの多角的な研究から、林業の未来を拓く可能性を探っていく。
保積 和奏
ほづみ わかな○2001年生まれ。大阪府高槻市出身。
幼い頃の原体験をきっかけに林業と《人》の関係に着目し、深刻な課題である担い手不足に斬り込む。
現場にこだわることが信条。宮崎や群馬、三重など各地に足を運んで現地調査を行い、「リアル」を論文に盛り込んだ。
森林・人間関係学研究室のゼミでは率先して場の調整役を担うなど、俯瞰的で高い客観性を持つ一面も。
《森林から木材利用まで》をひろく見渡し、
論文発表で社会還元を目指す
京都大学農学部・大学院農学研究科の森林・人間関係学研究室は、森林と人と社会の三側面から統合的に捉えた研究を推進している。森林所有・森林施業・素材生産の《川上》から、木材の流通・加工、建築や紙需要の《川下》、さらに政策・制度、環境評価まで、幅広いフィールドを扱う。一方で数式や統計で需給や貿易、価格などの市場を読み解き、他方で仮説を立て、国内外の現場調査での検証を重んじるのが特色だ。
研究室を率いる立花敏教授は、国の審議会や委員会などを通じて「森林・林業基本計画」をはじめとする林野庁などの政策にも意見を届け、産業界や市民とのネットワークを築きながら、積極的に産官学による協働に努めている。他にも、林業経済学会や日本森林学会、環境経済・政策学会など多数の学会に所属し、大日本山林会刊の月刊誌『山林』での連載や日本木材総合情報センター刊の月刊誌『木材情報』の編集にも携わる、生粋の《実践派》である。そんな立花教授が学生に求めるのは、調査や分析だけで終わらせず、「論文発表という活字にして社会へ返す」こと。学生たちは教授の手厚いバックアップを受けながら研究の設計から調査・分析、論文執筆までを通じ、得られた知見を社会に届ける力を養っている。
立花教授が目指すのは、「森林を減少・劣化させず、木を長く賢く使う社会の構築」である。修士課程2年、保積さんの「林福連携」研究もこの社会還元の視点から接続されたものであり、当事者の「働く」声をいきいきと捉え、課題に向き合うための実証への一歩を踏み出している。


「生きづらさをほどきたい」
社会貢献視点から生まれた設計図
保積さんが「社会と環境をマクロに捉えたい」と、農学部の森林科学分野を志したのは、幼い頃から“人と社会の関係”に関心を抱いていたからだ。子どものころ、周囲のいざこざをただ見ていることしかできず、「どうして人はこんなに分かり合えないんだろう」と感じたという。自分には何もできなかったという無力感と、そこから生まれた他者理解への関心 それが、のちに“人と社会の関係”を見つめる彼女の原点になった。
当時読んだ小説の一節 「メガネをかけることが『かわいそう』でないのと同じように、白杖を持つ人を『かわいそう』と思わない その言葉は、人の多様さを肯定する考え方として心に残っていく。
その後大学で学びを重ねるうちに、社会構造や人の生きづらさに対する感受性がより深まった。コロナ禍の息苦しさを経験したことで、「誰もが安心して関われる社会とは何か」という問いが、彼女を次の行動へと導いていく。
友人に教わった「農福連携」の現場を大学3回生のインターン参加で目の当たりにしたとき、霧が晴れて自身の進むべき道が現れた。「生きづらさを抱える人も、適性に合う作業に出会えさえすれば、楽しさや生きがいをもって働ける、という当たり前のことに気づかされたんです」。
「林業でも同じことができたら」 保積さんの発想はシンプルだったが、「林業は危険で特殊」という社会に広がる固定観念との折り合いが必要だった。しかし、三重県と宮崎県、群馬県で行った現場調査から見えたのは「作業の分節化」と「適性に応じた役割設計」という現場での工夫。それは制度が掲げてきた「人手不足の穴埋め」という一方的なアプローチではなく、誰もが働きやすい環境の再構築だったのだ。

障害のある人が働ける環境は、結果的に誰もが働きやすくなるユニバーサルデザインとなり、林業の労働環境改善を促せるという考えだ。
「制度と現場が《並走》することが最重要だと捉えています。目指すのは当事者にとっての働きやすさを実現することであり、現場知と当事者の声を共有しながら前進していく仕組みづくりが次の推進の核となるでしょう」。


「対話と観察」
徹底的に現場視点から深く掘り下げる
「林福連携」に関心を持った理由は?
保積 和奏(以下 保積)
障がいのある方をはじめ、現代社会で増加傾向にある、「生きづらさ」を抱える方々の働き方への関心が原点です。友人に教わった農福連携の現場から、「適性が合えば誰もが楽しく働ける」という実感を得ました。自身の専門分野である林業でも同様の展開が可能なのではないかと考えました。
これまで訪れた現場から見えた、林福連携の可能性とは?
保積 三重県の苗木管理現場や、宮崎県の森林組合と福祉事業所の連携、そして群馬県では福祉事業所の主導による、薪生産の実態を調査しました。実際に取り組まれていた作業としては薪や木工、苗木管理が中心で、安全性確保を行ったうえで各人の適性を軸に分節化されていました。
取り組みの形態は、先行研究や農福連携の事例にも見られるように、「組合と福祉の連携」「子会社による内包事業」「福祉事業所からの参入」といった複数のパターンがあります。林福連携の場合も、各現場や従事する人の適性をみて、こうした仕組みを柔軟に設計していくことが重要だと感じました。
「林福連携」が掲げる制度の目的と、現場の実態のギャップは?
保積 制度の目的としては「人手不足の解消」と「社会参画」が掲げられています。でも実際の現場では、工程の分節化や安全配慮、環境整備など、「当事者の働きやすさの実装」が中心です。苗木管理や木工といった分野では、季節・短時間就労のマッチングが進みつつありますが、伐木のような高リスク工程はまだ限定的。つまり「制度の目的」と「現場の取り組み」は対立するものではなく、互いに支え合う関係にあると思うんです。現場で得られた知見を言語化して共有することで、働きやすい環境を整えていく。それが長期的には担い手の裾野拡大や労働環境改善を通じた「制度の本来の目標」にも寄与し得ると考えています。
現場では、どんな工夫や配慮がされていると感じましたか?
保積 「安全」と「適性」の両立です。例えば、障がいのある方の「過集中しやすい特性」を見越して、時間で区切った休憩と水分補給を徹底するなど。作業前に、工程やリスクを丁寧に説明し、作業の流れを共有することで安心して取り組めるよう工夫されています。また、足元の凸凹を均して動線を確保し、転倒や疲労を防ぐ環境づくりにも取り組んでいると感じました。コンテナ苗では座ったままで培土・播種・挿し穂など標準化しやすい工程に再設計されています。結果的に障害の有無を問わず、誰もが働きやすい環境づくりにつながっていると思いました。
今後の研究と大学院修了の進路について教えてください。
保積 研究面では、修了までに宮崎・三重で当事者への聞き取りと参与観察を深め、必要な配慮や工程設計を言語化し共有。現場知を活字にして返し、林業の多様な関わり方を広げる土台づくりを続けます。
修了後は障害者雇用事業をグループ内で展開する民間企業に従事する予定です。将来的にはグループ事業の障害者雇用に関わる可能性も視野に入れ、加えてライフワークとして今後も現場や当事者と関わりながら、子ども食堂や里山ボランティアにも関与したいと考えています。


林業の未来を照らす
「社会科学的にも価値ある研究」
「制度」と「現場」を対立ではなく並走として捉え、それを実務で支える知の整備が必要だと捉える。保積さんは、当事者への継続的な聞き取りと参与観察を核に、休憩設計や事前説明、動線・足元整備、コンテナ苗での標準化といった配慮を実証的に言語化し、現場でそのまま使える指針として還元しようとしている。さらに橋渡しを行政に限ることなく社会福祉協議会や民間にまで視野を広げる他にも、A型・B型の制度分岐で分散しがちな求人導線をつなぎ直すことが重要だと考えている。
こうした積み重ねは多様な関わり方を当たり前にし、結果として林業全体の労働環境底上げが期待できる。立花教授が評価する「当事者の声を丹念に収集する姿勢」と「知見を活字にして社会に返そうという情熱」は、次の現場を動かす推進力そのものだ。現場の工夫を言葉にし、共有し、また確かめる往復運動を重ねることが、林福連携の価値を誤解なく社会へ届け、裾野を静かに着実に広げていく一本道となるに違いない。