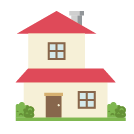言うまでもなく国内の過疎問題は年々深刻化している。様々な取り組みがなされているものの抜本的解決までにはなかなか結びつかない中、持続可能な取り組みとして注目されているのが《産官学連携》だ。学生と地域が協働することで新たな視点からの魅力発掘と若年層へのアプローチが期待できるほか、持続可能な地域づくりの新たな手法として期待されている。
岡山県北部の新見市もこの過疎化の例外ではない。2015年からの5年間で人口は8.4%減少し、高齢化率は41.4%に達するなど(※2020年実施・総務省国勢調査より)、県内でも過疎化が著しい地域の一つであり、若者の流出や担い手不足は深刻で、地域再生は喫緊の課題となっている。
そうした中で2020年に始まったのが、新見公立大学のSA(学生アシスタント)によるまちづくり活動である。活動は単なるボランティアではなく、報酬を伴う実践型プログラムであり、学生にとっては地域で働き学ぶ貴重な機会となっている。SAを入学理由に挙げる学生も増え、定員を超える希望者が集まるなど、人材確保の面でも成果を上げている。地域との連携は唐松地区のお祭りから始まり、下熊谷地区の福祉サロン、駅周辺の活性化プロジェクトを経て、2023年からは草間地区の地域活性化ミッションがスタート。期間2年を目処に行われてきた草間地区活動の2025年集大成を背景に、《SA学生のまちづくり活動》の意義と展望を探る。
SA学生のまちづくり活動
SA学生主体のまちづくり活動◯SA=Student Assistant(ステューデントアシスタント)。入学時に希望者の中から毎年20名程度を選抜、学内に設置されている「地域共生推進センター」に配属され、授業の空き時間や放課後を活用し有償で活動する。「学生自ら考え、地域へ働きかける《主体性》の育成」を狙いとした教育システムを構築。医療福祉系大学の枠組みを超えた取り組みとして話題を呼んでいる。
2025年8月現在、1〜3年生51名が在籍。主力として活動するのは1〜2年生の2年間である。
まちづくり活動は2020年10月よりスタート。大学が中心となり新見市内の地域に精通した専門職員(コーディネーター)やSA担当教員とともに、学生主体での地域課題解決を着地点とした様々な活動に取り組んでいる。
3つの部門から地域課題へアプローチ
2年間の活動で成果を狙う
岡山県の最西北端に位置する新見市は、2005年に旧・新見市と大佐町、神郷町、哲多町、哲西町が合併して誕生。千屋牛やピオーネなどの特産品と、国の天然記念物「羅生門」「鯉ヶ窪湿性植物群落」や「井倉洞」「満奇洞」など多くの誇るべき観光資源を有しながら、人口減少は加速度を増すばかりで、過疎化に歯止めがかかっていないのが現状だ。
移住・定住支援強化や産業支援などそれまで実施されてきた施策に加えて、2020年に新見公立大学の「SA学生のまちづくり活動」がスタート。産官学連携の要望は大きかったものの、医療福祉系の専門職養成大学であったために実現が難しかった。そこで岡山大学で地域づくりをテーマに実績を収めていた長宗武司氏を助教に招き、さらに学生を非常勤職員として雇用するSA制度を導入し、新たな挑戦が始まった。
活動は「地域交流」「駅西サテライト」「情報発信・広域連携」の3部門を柱に展開。「地域交流部門(まちづくりゼミナール)」では地域住民の要望に応える形で地域貢献活動を下熊谷と唐松、草間の3地域において実施した。「駅西サテライト部門」は、ワークショップやイベントなどを企画実施。2022年4月にオープンした新見駅横の大学のサテライト施設であるNiU新見駅西サテライトを地域交流の場として活用している。そして「情報発信・広域連携部門」は「フリーペーパーなるたき」やSNSでの情報発信、他大学との交流を通して大学や新見市の認知度向上を図っていく。これら3部門が一体となり活動の入口と出口を一本化している点も、持続可能な取り組みとしての広がりを後押ししている。




「大学生の皆さんがここまでやってくれるとは思わず、本当に嬉しかったですし、やってよかったと心から思っています」と話すのは、長年草間地域を市職員として支えてきた西村和夫氏。2023−2025年の草間地域交流プロジェクトのコーディネーターでもあり、市職員として観光振興に携わり、定年後も地域活動を続けている。
「祭りのときなんか、学生は前日から泊まり込みで調理室にこもって、夜中まで試作品を作っていたんですよ。よく考えて、一生懸命やってくれました。顔なじみになった住民も多く、世代を超えた関係が育ってきたのは地域にとって財産です」と振り返る。そうして生まれたのが、草間特産のそば粉を使った「くさま そば粉クッキー」。学生が住民と丁寧に対話を重ね、大学初の商品化第1号を実現した。さらに観光周遊マップ「くさまっぷ」を発行。新見の地で、新たな学生による地域貢献のプラットフォームが完成を見たのである。

長宗 武司
ながむね たけし ◯1991年生まれ。岡山県和気町出身。
新見公立大学 健康科学部 地域福祉学科 助教(専門は都市・地域経済学、地域公共政策)。「地域共生推進センター」SAの主担当教員。
岡山大学経済学部在学時に「スポーツと地域振興」をテーマとして地域づくりに携わり、同大学・大学院で経済学の博士号を取得。現在も研究や地域活動を続けながら助教として教鞭を執る。「地域共生推進センター」創設にあたり新見公立大学に着任し、当活動のキーマンとして学生をバックアップ。
地域共生推進センター
新見市の「大学を活かしたまちづくり」の推進と「新見版地域共生社会」の構築を目指し、2019年に地域連携の司令塔として新見公立大学内に設置された。学長をトップとし、大学教職員をセンター委員とする大学主体での地域活動拠点構築は全国でも稀有な例。
SAの学生は全員に役割が与えられ、本分である専門職養成のための授業をこなしながら週3コマ程度の活動を行っている。


地域×大学の協働
絶妙なマッチングが織りなすシナジー
草間地区の活動以外にも「駅西サテライト部門」の夏祭り「サテフェス」主催など、SA活動はその領域と地域からの期待が拡大し続けている。「SA活動によって、地域からの期待はますます高まっているのを感じます。 初めは“大丈夫だろうか”といった不安があるものの、取り組んでいくうちに“こんなこともできるのか”と驚きや称賛へと認識が変わる。それが“今後も一緒にやっていこう”という未来のアクションへとつながればいいなと思っています」と長宗助教は語る。
また、新見市と新見公立大学のマッチングでしか成し得なかった奇跡も存在すると言う。「私のような者が“大学の者です”なんて自己紹介したら構えられてしまうこともあるんですが、地元に精通したコーディネーターの職員さんが一緒だと、新見の方同士で垣根がない。製菓店さんもそうでしたが、中学校や高校に協働を呼びかけても“いいですね! やりましょう!”と二つ返事で協力いただけるんです。また、本学は看護・保育・福祉分野の専門職を目指している学生ばかりなので、高齢者と子どもに対するコミュニケーション力に長けています。責任感が強く一所懸命に取り組んでくれるので、学生が地域に受け入れられているんだと思います」。
長宗助教が院生のとき、地域づくりの中心的プレイヤーとして従事した自身の経験から、言葉に実感がこもる。「まちづくり活動において、実際に動けるプレイヤーは少なく、学生は貴重な存在です。約2万5千人の地域に800人の学生がプレイヤーとして存在する意義は大きく、年々、地域と学生の関係が変化しているのを感じます」。

専門知識習得だけにとどまらない
幅広い体験学習で人間力が高まる

白数 美月
しらす みづき ◯2004年9月生まれ。京都府与謝野町出身。
新見公立大学 健康科学部 看護学科 3年生。「地域交流」の部門を束ねるリーダー。小中高校と生徒会活動に参加、高校時代からはボランティアに携わるなど、地域活動に率先してかかわってきた経歴を持つ。明るく行動的で、周囲から頼りにされる存在。

駒野 桃香
こまの ももか ◯2004年5月生まれ。和歌山県和歌山市出身。
新見公立大学 健康科学部 看護学科 3年生。草間地区プロジェクトにおいて「そば粉クッキー」商品化を担当、製菓店との折衝やパッケージデザインなど幅広く携わった。周囲をよく観察し、冷静で素早い、的確な判断が持ち味。
「SA学生のまちづくり活動」に参加した理由は?
白数 美月(以下 白数) 高校時代からボランティアに携わり、多くの出会いや経験で視野が広がることを知りました。参加したのは、看護の勉強だけで大学生活を過ごすより、もっといろんな経験を通じて人として成長したいなと感じたのがきっかけです。それに、学内だけでは教員と学生だけと人間関係が狭いので、社会に出た際に関わりが深くなるご高齢者や子どもたち、幅広い年齢層と積極的に触れあっておきたいと思いました。
駒野 桃香(以下 駒野) 高校時代はコロナ禍で、クラブ活動も制限されていたので「大学では看護の勉強以外のこともやってみたい」という気持ちがありました。地元から離れた機会でもあるし、地元以外の地域活動に携わることができ、アルバイトの代わりにもなる貴重な経験だと感じました。それに、看護師は目的に合わせたケアや手順が決められています。もしかしたら私は、SA活動のような創造性の高い活動に飢えていたのかもしれません。
「SA学生のまちづくり活動」で大変だったことは?
白数 実際の活動までにやることがたくさんあって、本当に大変でした。イベント開催にしても、企画から計画立案、地域の方々との折衝を経てようやく形になります。企画だけでもやりたいことだけやればいいわけではなくて「開催地域の特長を活かそう」とか「子どもがメインだから、子どもとお母さんが一緒に楽しめるものに」など、参加いただく方々や開催時期、地域特性など幅広い視野を持つことが重要で、そうした細かい部分がすごく大事だし、大変だなと感じました。
全体のリーダーとして同時にいくつかのプロジェクトを進行させていく中で、いろいろな経験をさせてもらいました。
駒野 たくさんの方と関わり、トライアンドエラーを繰り返したことです。私が担当したのは「そば粉クッキー」の商品化で、もともと先輩が作製したレシピがあって、まずはお祭りで売ろうという話になりました。レシピはあったものの、そもそもどうやって商品化していくかもわからず、アイディアも出なくて苦労しましたね。草間地区のコーディネーター役の西村さんや地元の製菓店「青柳本舗」さんに協力をお願いして素材の吟味や味の調整から、販路開拓やパッケージデザインの変更などあらゆる側面を考えました。
SA活動は「お手伝いしました」という通過点ではなく、大勢の人と団体を巻き込む上に、一定の成果を出していかなければなりません。計画・段取りなど表面に出ないことが多くて思った以上に大変でした。
活動を通して発見できた新たな課題や、気づきはありましたか?
駒野 実際に地域で暮らしている方であっても、意外と地域の魅力は知らないのではと感じました。私も新見に来て3年ですが、活動をするまでは特産品や魅力的な場所について知らないことが多くありました。今回「そば粉クッキー」という特産品を通して草間地域の認知度向上を図りましたが、認知されることでもっともっと可能性が広がる。スポットに留まらず岡山県全体で同様の取り組みを推進すること重要なのではと思います。
また、SA活動で人の優しさや地域の魅力に触れられた経験はとても有意義でしたが、大学生視点では交通や買い物など生活インフラの不便さは、どうしても住みにくさにつながっていく要因になってしまう。活動範囲が狭くなるとどうしても「知る機会」が制限されてしまうんですよね。
活動経験を今後、どのように生かしていきたいと思われますか?
白数 「知る」というのはどんなことにおいても、とても重要だと感じています。私たちは大学卒業後看護師や保健師として社会に出ていきますが、どちらも地域と人を対象とする職業。まずは自分が働く地域について知ることから始めようと思います。
また、様々な年代の方々や普段関わりのない職業の方々と話したり、マスコミ取材を受ける機会をいただけたりと、幅広いコミュニケーション経験も、今後に生かしていきたいと考えています。


地域社会との良好な関係が
ウェルビーイングをつくる
草間地区の地域活動と、駅西サテライト部門最大のイベントとなる夏祭り「サテフェス」の幕が閉じたことで、SA活動はひと区切りを迎えた。しかし、すでに次のプロジェクトは始まっている。「大学の枠組みより大切なのは、地域と学生との関わりではないかと感じます。この関わりがしっかり構築されていれば、活動は自然に進化していくでしょう。実際、活動をきっかけに様々なサークルが学内で立ち上がっています。居場所づくりや子ども食堂の運営、子ども向けイベントなど、小規模な大学だからこそ連携の強さが発揮されて“私も”と波及効果が生まれている」と長宗助教。さらにSA活動の熱は、学内だけに終わらない。「SA活動でありがたかったのは、学生さんが草間だけでなく他地域ともかかわって、地域の未来を考慮した活動としての視点を持ってくださったことです。そのためには単発で終わらせず、継続することに意義があります」と西村さん。「一度つながった関係を途切れることなくつないでいけたらと考えています」と地域にもほのかな意欲の炎が灯っている。
長宗助教は、この活動の行く末を考えている。「まちに自分たちのほしいものがないなら、自分で作ればいい。学生だからできない、なんてことはありません。そして、新見の良いところも悪いところもすべて見てほしい。もちろん、新見に残ってほしい気持ちもありますが、地元に帰ってからもここで培った視点で活動や仕事をしてくれたらいいなと思います。ただ学内だけで過ごす学生とは違う、豊かな経験を持った人材になってくれるのではないかと思っています」。
現代日本の社会構造ではもはや、過疎化を止めることは難しい。しかし地域と地域に暮らす人々がわが町に誇りを持つことができ、幸福を感じられるのであれば、それもまた未来につながる地域型ウェルビーイングと言えるのかもしれない。